第35回 「景気」と「経済」
日本経済の失速とデフレからの脱却、景気回復に政府はアベノミクスで乗り切ろうとしているようだ。でも、実効のあがる経済政策の舵取りはなかなか難しいようである。アベノミクスの経済政策が正念場を迎えるのは、案外早いことになるかも知れない。
江戸時代、公共事業を増やして景気拡大を図った政治家が老中田沼意次(たぬまおきつぐ)である。意次といえば、相変わらず時代小説では悪役として君臨しているようだ。意次の膨張経済政策というか殖産経済政策が、そして世界に先がけて日本を金本位制にしたことなど、こんにちでは経済学の方面では意次の政治手腕は見直されているのに、小説家は不勉強である。
ところで、なぜ経済活動のことを「景気」と書くのだろう。「景気」とはもともと、自然現象の様子、気配、景色、眺望などを意味する文字であることは、漢字の母国である中国でも日本語でもおなじことである。このところ好況感というものを味わったことがないせいで、政府に八つ当たりしていると言われそうだが、「景気指標」は経済状況を他人事のようにただ眺めた結果を公表するだけだから、皮肉にも意味としてはピッタリである。
中国の「経紀(けいき)」(生活、商売する、売買の仲立人、旅商いする人の意味)という語が日本に渡ってきて、その「経紀」が「景気」という漢字と混用されたという、江戸時代からある説がどうも正しいようで、「経紀」を「景気」にすり替えたところに、経済活動とは模様眺めで人間の操作ではどうにもならない自然現象だとする江戸人の諦(あきら)めがあるような気がする。徳川幕府の経済政策は、それほどアテにならないものだったということでもある。
田沼意次の時代から「ふけいき」と人びとが盛んに言うようになる。「景気」よりも「不景気」という言葉のほうが先に生まれたというと、奇妙に思われる人が多かろう。
この「景気」とならびよく使われる言葉が「経済」である。江戸時代は「ケイサイ」と発音し、「ケイザイ」と濁らなかった。この言葉がやたら流行(はや)ったのも田沼時代からである。
田沼意次が失脚してすぐ、徳川家斉(いえなり)が14歳の若さで第11代将軍になると、戯作者の恋川春町(こいかわはるまち)は黄表紙(きびょうし)『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』で、家斉を延喜帝(えんぎてい)に寓して(図版参照)、「ケイサイとは何の事だ、夜食の菜(軽菜、軽い食事、お茶漬け)のことか」と家斉を経済オンチに描いてみせて読者の笑いを誘っている。この家斉は経済オンチのまま将軍を50年勤めた。
宰相たるもの経済オンチでは困る。かといって生半可(なまはんか)な考えで「景気」を抑揚させるだけで、庶民の口から「ふけいき」という諦めの言葉が出ないように願いたいものだ。
(お知らせ)
本コラムの執筆者・棚橋正博先生が、NHKカルチャーラジオに3月末まで出演中です。テーマは「江戸に花開いた『戯作』文学」。NHKラジオ第2放送、毎週木曜日午後8:30~9:00、再放送は金曜日午前10:00~10:30です。

右の延喜帝は徳川家斉、左の菅秀才は松平定信に見立てて描かれている。「経済」にうとい将軍を皮肉った場面。(『鸚鵡返文武二道』寛政元年〈1789〉刊より)
田沼意次…1719~1788。江戸中期の幕政家。明和4年(1767)に第10代将軍家治(いえはる)の側用人(そばようにん)、安永元年(1772)に老中となる。積極的な膨張経済政策をすすめ、江戸のバブル期ともいえる「田沼時代」を築いた。
徳川家斉…1773~1841。江戸幕府第11代将軍。一橋治済(はるさだ)の長男。天明7年(1787)将軍となり、田沼意次を排して松平定信を起用して「寛政の改革」を行った。
恋川春町…1744~1789。江戸中期の戯作者・狂歌師。駿河小島(おじま)藩士。本名は倉橋格。狂名は酒上不埒(さけのうえのふらち)。『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』によって黄表紙の作風をうちたてた。寛政の改革を風刺した『鸚鵡返文武二道』にかかわる召喚に出頭せず、その年に亡くなったことから、自殺説もとなえられている。
延喜帝…醍醐(だいご)天皇(885~930)のこと。平安前期の天皇。宇多天皇の第一皇子。藤原時平(ときひら)、菅原道真(みちざね)を左右大臣として天皇親政を行った。後世、延喜の治と呼ばれ、公家の理想時代とされる。
![]()

 不思議の国ニッポン!!
不思議の国ニッポン!! 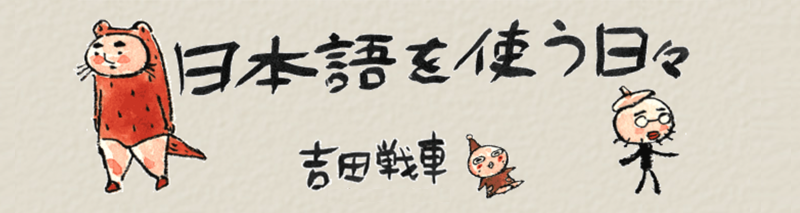 日本語を使う日々
日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記
日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言
女子大生でも気づかない方言  共通語な方言
共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝
山根一眞の調べもの極意伝 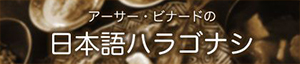 日本語ハラゴナシ
日本語ハラゴナシ 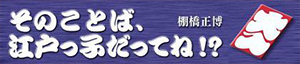 そのことば、江戸っ子だってね!?
そのことば、江戸っ子だってね!?