第1回 わが若き日の調べもの
2015年3月2日(月)山根一眞
ホームページは12億件を突破!
「調べる」ことほど楽しいことはない。
では、人はなぜ「調べる」のか? 「疑問」を持つからだ。
「疑問」は、何かを見て、何かを考えて、「謎」を見つけることで生まれる。「謎」とは、自分がその「答」を知らないことを意味する。「答」を知らないのは気持ちが悪い。「調べる」のは「謎」の「答」を知ってスッキリしたいからでもある。
「調べるなんて簡単、ネットで何でもわかるから」と、思うかもしれない。
実際、2014年9月16日に、世界のホームぺージの数は10億件を突破したと伝えられた。以下のインターネットのリアルタイムの統計ページを見ると、その情報量が爆発的に増大していることが実感できる。
http://www.internetlivestats.com/
ここでは、すでにホームページ数が12億件を超え、30億人という世界のインターネットユーザーが、Googleで1日あたり8億件近い「調べもの」をしていることがわかる(2015年2月17日現在)。
とてつもない情報量だ。昨年の12月にチェックした時と比べると、2ヶ月間にホームページだけでも約1億件増えていた! ネットが爆発的な情報増大を続けていることには驚くばかりだ。「ない情報はない」とすら思える。
ところが現実は、「調べるなんて簡単、ネットで何でもわかるから」というわけにはいかない。
たとえば、インターネットの商用サービスが始まったのは1994年。そのため、それ以前の情報はネット上ではガクンと少ない。1990年代以前のことを調べるには、当時の雑誌や新聞、書籍が欠かせないのである(古い印刷媒体のPDF化が進んではいるが)。
阪神・淡路大震災の写真が少ないわけ
インターネットは画像や映像も豊富だが、ネット上で検索できる写真は1995年以前のものとなると、これもきわめて少なくなる。
これは、一般ユーザーが手にできた最初のデジタルカメラの登場が1995年4月(カシオのQV-10)からだったからでもある。

デジタル写真であればネットへの掲載はとても簡単だが、それ以前は銀塩フィルムを使っていたので、それをスキャンしデジタル化する作業は手間がかかるからなのだ。
2011年3月の東日本大震災関連の写真は莫大な量がネット上で閲覧できるが、1995年1月の阪神・淡路大震災の写真はほとんどが報道機関によるもので、数もきわめて少ないのはそのためだ。

また、ネット上の情報はじつに「重複」が多い。私が、取材にもとづいてネット上に書いた記事をGoogleで検索したところ、見覚えのないウェブやブログなどでたくさん見つかった。それらはいずれも、私が知らないうちに私の記事を転載アップしたものだった。
その数があまりにも多く、またそれぞれのウェブやブログは、「書いている人」の氏名も所属も連絡先も記載していないことがほとんどだ。
こういうネットならではの「コピペ」発信の増加によって、ネット上の情報は、どれがオリジナルでどれがオリジナルからの引用転載なのかの判別がとてもしにくくなっている。出典や執筆報告者の記載のない情報に頼るのは、常に注意が必要なのだ。
また、オリジナル情報といえども必ずしも正確とは限らない。
ウソも含まれているかもしれないし、意図的に事実を曲げて伝えているかもしれない。だからこそ、その引用掲載をする場合には、もとのオリジナル情報を検証した上で、間違いがあればそれを指摘した上で伝えるべきなのだが、そういうケースも少ない(それを行う場合も、執筆報告者名を記すべきだが)。
論文でもニュース記事でも身近な問題でも、それは変わらない。情報で怖いのは「鵜呑み」なのである。「朝日新聞問題」はそのことの重要性に光が当てられたできごとだった(「鵜呑み」と書いたところで、鵜を使う漁法について調べたくなった……)。

 不思議の国ニッポン!!
不思議の国ニッポン!! 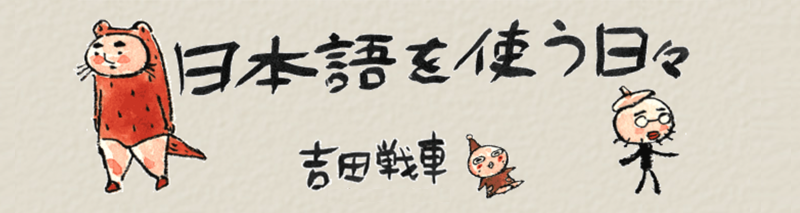 日本語を使う日々
日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記
日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言
女子大生でも気づかない方言  共通語な方言
共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝
山根一眞の調べもの極意伝 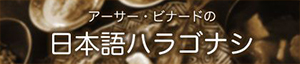 日本語ハラゴナシ
日本語ハラゴナシ 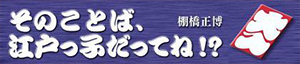 そのことば、江戸っ子だってね!?
そのことば、江戸っ子だってね!?